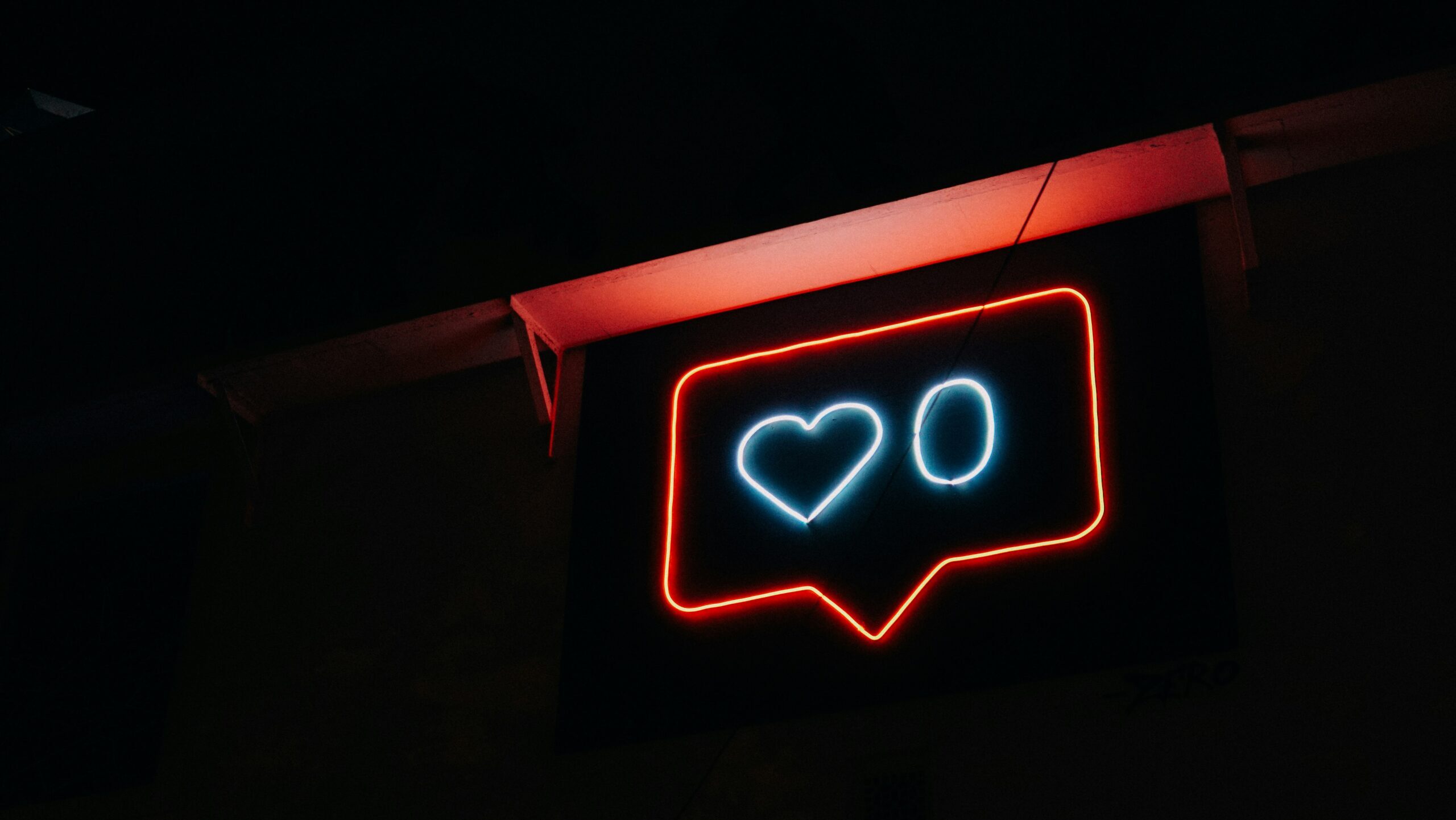私たちが普段、ネットで目にする『ニュース』『プレスリリース』には、一般の消費者が知らないマーケティング手法が隠されています。その中でも特筆すべきものが、プレスリリースサイトを利用した権威性の偽装です。一見、この手法は合法で問題がないように見えますが、消費者に誤解を与える要素を多く含み、時に意図して悪用されることもあるのです。
この記事では、PRサイト(プレスリリースサイト)を使った権威性偽装の手口と目的、一般消費者が注意すべきポイントについて、わかりやすく解説します。
『プレスリリースサイト』とは?
プレスリリースサイトとは
「PR TIMES」「ValuePress」が大手
プレスリリース(PR)サイトとは、企業や個人が自社の商品やサービス、活動について広く周知するためのプレスリリースを配信するプラットフォームです。代表的な例として、「PR TIMES」「ValuePress」などがあります。
これらのプレスリリースサイトでは、掲載を希望する企業や個人の側が料金を支払い、自分たちのニュースを配信してもらうことができます。
プレスリリースサイトにニュースを掲載すると、Googleなどの検索エンジンで上位に表示されやすくなったり、『Yahoo!ニュース』などのニュースサイトに引用されやすくなります。すると、仮にそれが怪しいセミナーやオンラインサロンの告知だったとしても、信頼性・権威性の高い情報だというふうに誤認してしまう恐れがあるのです。
詐欺師の「権威性偽装」にPRサイトが利用される理由
1.自分の名前や商品が有名企業のニュースと並んで表示されることを悪用し、権威性を誤認させる
PRサイトでは、スタートアップ企業や個人事業主のプレスリリースも、有名企業のニュースと並び、同じ形式で表示されます。
そのため、たとえ無名の個人、時に詐欺師が掲載したニュースであっても、「あの有名企業と同じレベルで認知されている人なんだ」と誤認させることもできるわけです。
例:
2. ニュースサイトに掲載される仕組み
PRサイトで配信された情報は、Yahoo!ニュースやGoogleニュースなど、信頼性が高いと一般消費者には思われているメディアに引用されることがあります。
これにより、講師側が掲載料を払って出した記事が、広告ではなく中立的なニュース・取材された記事であるかのように見えてしまいます。
カラクリを知らない一般消費者に対する危険性
1. 講師の実績・情報を、信頼性が高いものだと思い込ませる
ここまでお話したように、PRサイトには、掲載料を支払えば誰でも自社のニュースを載せることができます。もちろん真っ当な会社がほとんどですし、プラットフォームを利用したマーケティング戦略それ自体に問題があるわけではありません。
しかし、PRサイトに載っていたから絶対に信用できる、とは言えないことが、その仕組みを知ればわかると思います。PRサイトの性質や掲載の仕組みは、Webマーケティングに馴染みがない一般の方にはあまり知られていないことだと思いますし、実際そのことを利用している詐欺師は存在します。
2. 広告だと気づきにくい(結果として騙している)
PRサイトで配信された記事は、仮にそれが詐欺的商売の告知であったとしても、見た目が一般的なニュース記事とほとんど同じです。多くの消費者は、これが広告の一種だとは気づきません。これは、結果として消費者をだましているのと同じであるといえるかもしれません。
詐欺師がPRサイトを利用する理由
中身のない企業や個人がPRサイトを利用する理由はシンプルです。「簡単に信頼性を演出できる」「権威性を装える」からです。
お金さえ払えば掲載してもらえる
一般に、無料~数万円の掲載料さえ払えば、プレスリリースサイトにニュースレターを配信することはできます。
検索エンジンで上位に表示される・情報を拡散しやすい
PRサイトを使うことで、有名ニュースサイトや検索エンジンでヒットさせることができます。個人で運営するホームページで告知するよりも検索順位が格段に上がりやすく、かつ、有名ニュースサイトに引用されることで、さらに情報は拡散します。
権威性を偽装できる・大企業と同列に見える
お金さえ払えば、大企業のプレスリリースとほぼ同じ見た目の記事を、同列に配信してもらうことができます。ニュースレターを出稿している企業側がプレスリリースサイトに掲載料を払っていることは、意外と気づかれていない盲点であると言えます。
騙しやすい・誤認させやすい
有名企業と並んでニュースが配信されることで、それが実質は広告であることを知らない一般消費者は、詐欺師の商品の告知であったとしても、信頼性が高い情報であると錯覚してしまいます。実際に、その効果を悪用し、だまそうとしている悪質な講師もいるのです。
消費者側で自衛する方法
記事の出所・メディアの収益源を確認する
ニュース記事の中に「PR」や「提供」の表記がある場合、それは広告の一種である可能性が高いです。そのメディアを運営しているのは誰で、どこから収益を得ているのかチェックすれば、そのニュースの信頼性を見抜くヒントになります。
PRサイトを一度出て、商品・販売者の評判を再検索する
特定の商品・サービスについての情報をプレスリリースサイトで得た場合、一度そのPRサイトから出て、一般的な検索エンジンでも同様の良い評価が確認できるか、必ず調べてください。Googleなどの各種検索エンジンで普通に調べても、その講師の公的な情報は出てくるのか。
検索エンジンでプレスリリースサイトの講師を調べると、さまざまな肩書や実績をうたっている割には講師自身のブログ・SNSしかヒットしなかったり、実績があってもその相手も怪しい講師である場合が少なくありません。
他にも、講師がセミナー・自費出版などをしている場合、複数のサイトで口コミを確認しましょう。批判的なものも含めて情報を多角的に検証することで、権威性の偽装や優良誤認狙いを見抜くことができるかもしれません。
派手な宣伝文句は警戒する
「簡単に成功できる」「驚異的な効果がある」などの過剰な表現が含まれている場合は、一歩引いて冷静に検討しましょう。
まとめ:プレスリリースサイトを利用した権威性の偽装を見抜く
プレスリリースサイトは企業や個人にとって有効なマーケティングツールであり、当然、合法的なサービスです。しかし、その性質を巧みに利用すれば、消費者に誤解を与えることもできてしまいます。
どのマーケティング手法にも言えることですが、その手法自体が必ずしも悪いわけではありません。それでも、様々なマーケティングツールの特性を利用して誤認を狙う手口、影響力・権威性の偽装を行う手口について知識があれば、怪しいコンテンツや講師を見抜く助けになるでしょう。
「どこで発信された情報なのか」「その情報は中立的か」を意識して判断することが大切です。インターネット上の情報は玉石混交ですので、自分で見極める力を養うことが、賢い選択につながります。